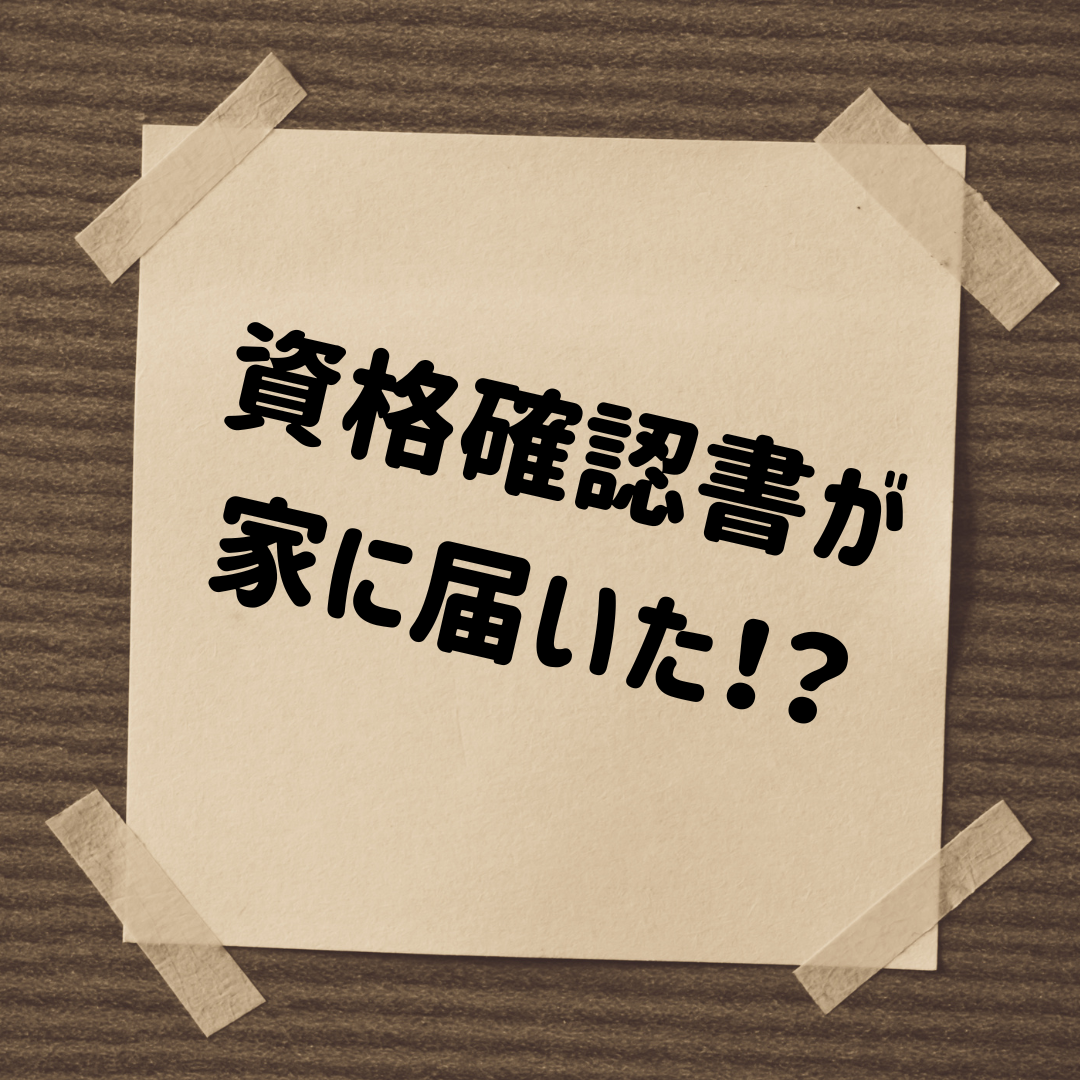Date: 2025/10/23
こんにちは、ワールドワイド社労士事務所です。
企業の総務・人事ご担当者様の中には、
「『資格確認書』が届いた」と連絡を受けている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、資格確認書について基本的な内容から、従業員への説明ポイントを分かりやすく解説します。
そもそも「資格確認書」とは?従業員への案内のポイント
「資格確認書」とは、マイナ保険証をお持ちでない方が、これまで通り保険診療を受けるために必要となるものです 。
2025年(令和7年)12月2日をもって、現在お使いの健康保険証は使用できなくなり、
その後は、マイナ保険証を利用して医療機関を受診することが基本となります。
その際、何らかの理由でマイナ保険証を利用できない方のために、この資格確認書が発行されます 。
【資格確認書が交付される対象者】
対象となるのは、2024年11月30日までに健康保険に加入された方で、2025年4月30日時点でマイナ保険証の利用登録をされていない方です 。
【従業員への説明ポイント】
従業員から問い合わせがあった際は、
まず「資格確認書があれば、これまで通り健康保険を使って病院にかかれます」と伝えることが重要です。
なぜ資格確認書が届いたのか、その理由を説明しましょう。
具体的には、以下のようなケースが該当します 。
①マイナンバーカード自体をお持ちでない、または協会けんぽ等の保険者にマイナンバーを提出していない場合
②マイナンバーカードは持っているが、健康保険証としての利用登録を行っていない場合
③マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限が切れている場合
よくある質問と回答の例
ここでは、想定される主な質問と、その回答例をまとめました。
問い合わせ対応の参考にしてください。
Q1. 家族の分も含めて、全員分の資格確認書が届かないのはなぜですか?
A1. 資格確認書は、マイナ保険証の利用登録をされていない方のみにお送りしています 。
ご家族の中に、既にマイナ保険証の利用登録を済ませている方がいらっしゃる場合、その方の分の資格確認書は発行されません 。
Q2. 以前にも資格確認書が届いたのですが、また新しいものが届きました。どちらを使えば良いですか?
A2. 資格確認書の右上にある「交付年月日」をご確認ください 。
日付が新しい方の資格確認書をご使用いただくことになります 。
なお、古い日付のものは、同封されている返信用封筒にてご返却ください 。
Q3. 今持っている紙の健康保険証は、どうすれば良いですか?
A3. 現在お持ちの健康保険証は、2025年(令和7年)12月1日までは使用できます 。
しかし、翌日の12月2日以降は効力を失い、健康保険証として使用できなくなりますので、ご自身で破棄してください 。
ただし、12月1日以前に退職などで資格を喪失した場合は、従来通り会社へご返却いただく必要があります。
マイナ保険証への移行、従業員にメリットをどう伝える?
メリット1:より質の高い医療が受けられる
マイナ保険証を利用すると、本人の同意があれば、過去の薬剤情報や特定健診の情報を医師や薬剤師と共有できます 。
これにより、重複投薬のリスクを回避できたり、より的確な診断や治療につながったりと、医療の質が向上します。
メリット2:高額な医療費の窓口負担が自動で軽減される
従来、入院や手術などで医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を事前に申請・取得し、窓口で提示する必要がありました。
しかし、マイナ保険証を使えば、この手続きが不要になります 。
マイナ保険証を提示するだけで、自己負担限度額を超える支払いが自動的に免除され、一時的な高額な立て替え払いが不要となります。
これらのメリットを伝えることで、従業員が自発的にマイナ保険証の利用登録を進めるきっかけになるでしょう。
まとめ
・2025年12月2日から現行の健康保険証は利用不可となり、マイナ保険証が基本となる。
・マイナ保険証を持っていない方には、保険診療を受けるための「資格確認書」が送付される。
・企業は、従業員からの問い合わせに備え、資格確認書の役割や各種手続きについて正確に理解しておく必要がある。
・従業員へは、マイナ保険証の利便性(医療の質向上、高額療養費制度の自動適用など)を伝え、利用登録を促すことが望ましい。
まずは、自社の従業員構成を確認し、マイナ保険証の利用状況を把握することから始めてみてはいかがでしょうか。
本記事に関するご不明点や、労務管理全般でお困りのことがございましたら、
お気軽にワールドワイド社労士事務所までご相談ください。